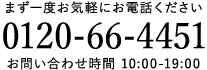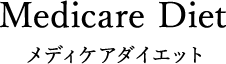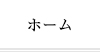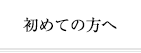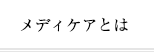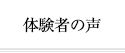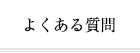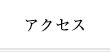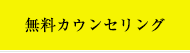カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2024年2月 (5)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (7)
- 2023年9月 (3)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (2)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (8)
- 2023年1月 (13)
- 2022年12月 (17)
- 2022年3月 (1)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (7)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (11)
- 2020年11月 (7)
- 2020年10月 (8)
- 2020年9月 (17)
- 2020年8月 (10)
- 2020年7月 (13)
- 2020年6月 (26)
- 2020年5月 (16)
- 2020年4月 (14)
- 2020年3月 (17)
- 2020年2月 (24)
- 2020年1月 (9)
- 2019年12月 (5)
- 2019年10月 (2)
- 2019年7月 (5)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (10)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (5)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (54)
- 2017年10月 (3)
- 2017年9月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (6)
- 2017年5月 (3)
- 2017年4月 (4)
- 2017年3月 (3)
- 2017年2月 (11)
- 2017年1月 (7)
- 2016年12月 (6)
- 2016年11月 (20)
- 2016年10月 (16)
- 2016年9月 (24)
- 2016年8月 (31)
- 2016年7月 (11)
- 2016年6月 (7)
- 2016年5月 (3)
- 2015年12月 (1)
最近のエントリー
HOME > メディケアコラム > 1日のたんぱく質必要量とは?
メディケアコラム
< 健康診断項目の内容 血糖・腎機能編 | 一覧へ戻る | 健康診断の基本を知りましょう 前編 >
1日のたんぱく質必要量とは?

みなさんは、たんぱく質を意識して摂取することはありますか?
たんぱく質を摂れる食品として、肉、魚、鶏卵、大豆・乳製品が挙げられます。
これらの食品の何をどれだけ食べたらよいか?
ここでは、適量を勉強していきましょう。
まずは自分の適正体重を計算しましょう。
日本肥満学会が提唱する、病気になりにくい健康的な標準体重の計算方法は、
標準体重=身長(㎝)×身長(㎝)×22
肥満判定で使われるBMI値の計算方法は、
BMI値=実際の体重(㎏)÷身長(㎝)÷身長(㎝) です。
因みにこのBMI値の健康的な標準範囲は、
18.5~25.0
となり、18以下は痩せすぎ、25以上は肥満気味~肥満となります。
身長が170センチの場合
1.70×1.70×22=63.6㎏
この体重が最も病気にかかりにくく、最も適正な体重であり、
たんぱく質摂取量の目安としてこの体重の数値がポイントになります!
つまり、健康維持に必要なたんぱく質量摂取の目安として
身長170センチのかたは、1日当たり約63~64gが最低必要量になります。
1日に必要なたんぱく質量= 体重63kg×体重1kgあたりに必要なたんぱく質量1.0~1.2g=63~75g が理想です。
キロカロリー換算すると、252~300キロカロリーほどになります!
普段の日常生活を送る方は、この摂取量が理想で、運動する方は摂取量が増加します。またダイエット中のかたは、食事制限などにより不足しがちで、せっかく努力して体重を落としても、体脂肪だけでなく筋肉量も落としてしまうかたも多いです。
それだけ、たんぱく質は必要な栄養素なのです!
では、「たんぱく質食品はどれだけの量を食べればいいの?」
と思いますよね! その目分量を見ていきましょう。
例えば、身近な食品だと、
納豆1パック当たりで、たんぱく質量は7g程度
鶏卵1個当たりで、たんぱく質量7g程度
牛乳コップ1杯150g当たりで、たんぱく質量5g程度
鮭の切り身1匹100g当たり、たんぱく質量20g前後程度
豚肉肩ロース脂身付き100g当たり、たんぱく質量17g程度
身近に目にするような食材を挙げてみました!
他の食品の成分が気になるかたは、市販で売られている食品成分表を参考にするのがおすすめですよ。
少し参考に挙げただけでも、自分の普段の摂取量が過剰か不足かも目安になると思います。
自分の1日に必要なたんぱく質量が把握できれば、これらの食品を1日の食事で分けることで1食の量を調整しやすくなります。
ただ、たんぱく質を含む食材には脂質も付きものです。
食材の選び方や、調理方法により無駄な摂取を抑える事ができます。
買い物でヒレ、ムネ、モモ、ささみなど脂身が少ないものを選んだり、下ごしらえで皮や脂身を剥いだり、調理では湯通しをしたりするなどでカロリーカットができます。
何をどれだけ食べたらよいか? と思うかたは、たんぱく質が不足気味で、脂質や炭水化物の摂取に偏るかたが多いです。
食事改善のきっかけとして、まずはたんぱく質の摂取を意識して摂る事から始めてみてもいいかもしれないですね。
メディケアでは、たんぱく質をいかに上手に摂取するかの指導も行なっております。必要量が,なかなか摂りにくい「たんぱく質」。自分ではわからないというかた、ぜひ初回無料カウンセリングを受けてみて、そのあと一緒に頑張ってみませんか?
たんぱく質を摂れる食品として、肉、魚、鶏卵、大豆・乳製品が挙げられます。
これらの食品の何をどれだけ食べたらよいか?
ここでは、適量を勉強していきましょう。
まずは自分の適正体重を計算しましょう。
日本肥満学会が提唱する、病気になりにくい健康的な標準体重の計算方法は、
標準体重=身長(㎝)×身長(㎝)×22
肥満判定で使われるBMI値の計算方法は、
BMI値=実際の体重(㎏)÷身長(㎝)÷身長(㎝) です。
因みにこのBMI値の健康的な標準範囲は、
18.5~25.0
となり、18以下は痩せすぎ、25以上は肥満気味~肥満となります。
身長が170センチの場合
1.70×1.70×22=63.6㎏
この体重が最も病気にかかりにくく、最も適正な体重であり、
たんぱく質摂取量の目安としてこの体重の数値がポイントになります!
つまり、健康維持に必要なたんぱく質量摂取の目安として
身長170センチのかたは、1日当たり約63~64gが最低必要量になります。
1日に必要なたんぱく質量= 体重63kg×体重1kgあたりに必要なたんぱく質量1.0~1.2g=63~75g が理想です。
キロカロリー換算すると、252~300キロカロリーほどになります!
普段の日常生活を送る方は、この摂取量が理想で、運動する方は摂取量が増加します。またダイエット中のかたは、食事制限などにより不足しがちで、せっかく努力して体重を落としても、体脂肪だけでなく筋肉量も落としてしまうかたも多いです。
それだけ、たんぱく質は必要な栄養素なのです!
では、「たんぱく質食品はどれだけの量を食べればいいの?」
と思いますよね! その目分量を見ていきましょう。
例えば、身近な食品だと、
納豆1パック当たりで、たんぱく質量は7g程度
鶏卵1個当たりで、たんぱく質量7g程度
牛乳コップ1杯150g当たりで、たんぱく質量5g程度
鮭の切り身1匹100g当たり、たんぱく質量20g前後程度
豚肉肩ロース脂身付き100g当たり、たんぱく質量17g程度
身近に目にするような食材を挙げてみました!
他の食品の成分が気になるかたは、市販で売られている食品成分表を参考にするのがおすすめですよ。
少し参考に挙げただけでも、自分の普段の摂取量が過剰か不足かも目安になると思います。
自分の1日に必要なたんぱく質量が把握できれば、これらの食品を1日の食事で分けることで1食の量を調整しやすくなります。
ただ、たんぱく質を含む食材には脂質も付きものです。
食材の選び方や、調理方法により無駄な摂取を抑える事ができます。
買い物でヒレ、ムネ、モモ、ささみなど脂身が少ないものを選んだり、下ごしらえで皮や脂身を剥いだり、調理では湯通しをしたりするなどでカロリーカットができます。
何をどれだけ食べたらよいか? と思うかたは、たんぱく質が不足気味で、脂質や炭水化物の摂取に偏るかたが多いです。
食事改善のきっかけとして、まずはたんぱく質の摂取を意識して摂る事から始めてみてもいいかもしれないですね。
メディケアでは、たんぱく質をいかに上手に摂取するかの指導も行なっております。必要量が,なかなか摂りにくい「たんぱく質」。自分ではわからないというかた、ぜひ初回無料カウンセリングを受けてみて、そのあと一緒に頑張ってみませんか?
(メディケアダイエット東京) 2016年9月14日 15:36